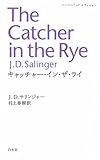Happy Holiday Seasons! 最近Happy New Yearは政治的正しさの観点からよろしくないと聞いて、さっそく使ってみました。確かにみんながみんな1/1に新年を迎えるわけではないので、これは納得(イスラム教徒とか)。Happy Merry Christmasはまずい(キリスト教以外の人もいる)というのは知っていたのですが。
それはさておき、昨年末にいくつか動きがあり、それらのほとんどは今年の目標などと関係しています。せっかくですし、自分への戒めという意味も込めて、ブログに書き残しておきたいと思います。
Qiitaにお引越し
年末にあった大きな動きとしてはまずQiitaのアカウントを取得しました。そもそもこのブログはプログラミングと日々の読書について書くために設立したものですが、とりわけ前者についてはやはりはてなブログだと限界があり、この際思い切ってお引越ししました。この見込みは大正解。すでにQiita上にいくつかの記事を公開していますが、非常にやりやすい。アクセス数も段違いに多く、なかなかいい感じです。なお今まではてなブログ上に公開してきた記事をQiitaにインポートするというようなことは考えていません。
おそらくこのブログは読書記録および自分の近況報告の場になると思います。アクセス数的に読書関連がメインコンテンツとなり果てていたので、まあ順当なところに落ち着いたかと。また自分の意見や考えを発表できる場を持っておくと、何かあったときに役立つと信じております。なお読書日記については当分の間、週に1度の投稿にする予定です。実際はもう少し読んでいますが(週に2-3冊)、あまり頻繁に投稿するとストックがなくなってしまう可能性があるため、やや控えめに進行したいと思います。なにせこの4月から社会人なので、読書にどれだけ時間が取れるかわからないのです(´・ω・`)。忙しすぎて、全然読めなくなくなったりして……(就職先が外資なので、これが全く笑えないという)
昨年はSchemeに取り組み、実りが非常に多かったと感じています。一番は再帰と末尾再帰の使い方が格段にうまくなったことですが、それ以外にも遅延評価や継続など、手続き型言語では学べない部分に触れられたのはとてもよかったと思います。――が、実用性という点でいうとちょっと口ごもらざる得ないというかなんというか。書くまでもないですが、実用的なソフトウェアを作る際に定番といえるような処理系がないSchemeをわざわざ選択する理由はないと思います。そこで今年はもう少し実用という点で優れており、かつ自分が詳しいといえるRubyおよびSchemeとはパラダイムが違う言語――すなわち手続き型の影響が強いものを探した結果、今年はPython Yearとなることが決定しました。
ちなみに選定基準としてはまず動的であること(たまにC言語の型で苦しむから)、そして手続き型の影響が強い実用的な言語に絞ったところ、ほかにPerl6やPHPが候補に挙がったのですが――Perl6はソースコードの見た目が自分の美的感覚に合わず、PHPは実用的とはいえひとつの言語としてみたときには出来がよろしくないということで、Pythonを選んだのでした。当面はCheckIOやCodeIQでPythonを書く練習をしつつ、こなれてきたらコードリーディングをしていくつもりです。将来的には何かしらのソフトウェアやライブラリが公開できればいいなと妄想しています。
もっともSchemeをやめる気はありません。これからもちょこちょこ書いていこうと思います。RubyとSchemeが好きということからもわかる通り、わたしのプログラミング脳は関数型にチューンナップされており、ときおり無性に関数型言語に触れたくなります。たぶんそういうときにSchemeで遊ぶはず。とくにCodeIQではSchemeを利用することが認められているので、主戦場になると思います。
エディタを変えました。ここ2-3年はSublime Text3(以下ST3)を利用していたのですが、あれは一応シェアウェア。無料でも全機能が問題なく使えますが、ただで利用しているという妙な負い目があって、ATOMへと切り替えました。ATOMは完全なフリーウェアなので気兼ねなく使えます。またどのOSでも使えるというのがまたGood(いまはWindows10を利用しているのですが、Linux/Macの導入も考えているので)。
もっとも不満がないわけではなく……。はっきりいうとST3の方が使いやすいです(´・ω・`)。メモリを食うわりにはもっさりしており、機能面でもかゆいところに手が届かないような作りになっています(自分で作れということかしら)。とくにあのGitHubが作ったにも関わらずGit連帯がしょぼいとはどういことなのか! 現状はちょっとプログラミング向きのエディタという程度の印象ですね。まあまだまだ開発途上のエディタなので、気長に付き合っていこうと思います。
ちなみにATOMにたどり着く以前に、最近話題のVisual Studio Codeも試しています。使っていないということは要するにそういうことだ。劣化版のATOMという感じです。しかしこちらはGit関連の機能が超充実しているという……。なぜでしょう?
とりあえずプログラミングに限っていえば、この程度でしょうか。もちろんそれ以外にも抱負といえるようなものはいくつもありますが、それはおいおい。とりあえず現在進行形の糖質制限(ダイエット)を耐え抜くこと。あとは何事もなければ今年大学卒業&就職なので、社会人として頑張りたいと思います。就職先はいわゆるSIerですが、配属は希望していない技術営業になりました……。PG/SEを散々希望したはずなのに、どうしてこうなった(´・ω・`)。そういう意味でも波瀾の1年になりそうです。退職エントリだけは書くことがないよう頑張っていきたいと思います。