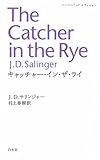2-3年ほど前だが、カウンセリングにかかっていたことがある。カウンセラーいわく「自律神経失調症」。当時のわたしは特に理由もなく不安になっては胸が苦しくなるほど心拍数が上がったり、脂汗を滝のようにかいたりしており、それは典型的な自律神経失調症の症状だったらしい。その後1年ほど週に1度のカウンセリングに通った結果、精神面は回復、ここ1年ほどはまったくの無事平穏に暮らしてきたのだが――最近になってあのときのような症状が再発しつつあるように感じている。つまり理由もなく不安に陥るのである。もっとも昔のように身体的な症状が出ていないのが救いであるが、しかしいつ再発してもおかしくない。
実のところ「再発」の理由ははっきりしている――大学卒業にかかわるストレスだ。わたしは大学5年生(就職留年している)であり、今年卒業なのだが、「本当に卒業できるのだろうか」という始終とりつかれている。「履修に失敗しているのではないか」「履修を管理するためのWebサイトの表示が誤っているのではないか」「すでに提出した卒業論文がリジェクトされるのではないか」――などなど、悩みというより被害妄想はまったくつきない。
わたしがふつうの4年生であれば、そのような杞憂に精神をすり減らすことはなかっただろう。少なくとももう少し気楽でいられたはずだ。しかしわたしは留年生であり、何があろうとこの3月に卒業せねばならない。単なる留年でも多くの人に迷惑をかけたのだ。これ以上留年はできないし、仮に留年してしまうと学部2留となり社会的な不利益がさすがに大きすぎる――いわば背水の陣にわたしはおり、それが多大なプレッシャーとストレスになっていることは想像に難くない。
ならば時がきて卒業が確定すればストレスから解放されるのだろうか――おそらくそれはない。わたしの杞憂あるいは妄想と原因となっているのは卒業がらみのことが大きいが、就職も要因として大きいことは否定できないからだ。もともとわたしはプログラマもしくはシステムエンジニアを希望して就職活動を行い、そこそこ知名度もある外資系SIerから内定をもらったのだが、どうやら希望の職にはつけないということが明らかになりつつある。つまりSE/PG志望のはずが、ふたを開けてみると配属先は技術営業らしいのだ。
技術営業が悪い仕事とは思わない。会社の屋台骨を支えているのはかれらであることは間違いないだろう。しかしそれはわたしが希望する職種ではないのだ。入ろうとしている会社は外資系で知名度があり、給料もそこそこ、研修や福利厚生なども手厚いらしく、新卒カードを切るだけの価値は十分あったというのは今も間違っていないと思う。なにより散々迷惑をかけた両親が喜んでくれているのが、個人的にはとてもうれしい。しかし技術営業という職種に関心がわかないのもまた確かなのだ。面接や人事面談では開発を希望していることを告げたはずだが、どうしてこうなったのか。
新入社員はまるまる1年間研修なのだが、それだけ受けて転職することも考えている。「プログラマ35歳定年説」ということばがあり、時折その賛否が話題になるが、しかし若いうちが華である職業であることは間違いない。少なくとも十人並の自分の能力を考えると、プログラマとして最前線で働けるのは35歳かそこらまでだろう。いまのわたしは23歳。したがって「定年」まで12年間しかない。干支でいえばたった1周である。はっきりいって焦りしかない。
幸運にもこの日本には第2新卒という枠組みがあり、職業あっせん会社も力を入れている領域である。それにIT系はおりからの好景気で売り手市場と聞く。待遇さえ選り好みしなければ、希望するSEやPGとして働くことができるだろう。しかし「あのつらかった就職活動を働きながら続けねばらないのか」と考えると、今から憂鬱な気分になる。また仮に転職するにしても、当面は業務としてのコードを1行も書かない1年間を送らねばならない。長い人生のたった1年と考えれば短いかもしれないが、IT業界の1年は途方もなく長い。長すぎる。Rails8ぐらいになっていてもおかしくない。自分が技術営業として研修を受けている間、世界は何千歩何万歩と進み、自分だけ取り残される――そんなことを考えていると気が狂いそうになる。自律神経失調症もぶり返すわけだ。
もう一度カウンセリングなり精神科なりを受診すべきかしら? 大学にはカウンセリングの窓口があり、行くとすればそこだが、いつも予約でいっぱいなので、もうまもなく卒業する人間がかかるのはかなりしのびない。それに身体に悪影響が出ているわけではなく、日常生活もふつうに行えている(以前は影響ありまくり)ので、大金をはたいて外部のカウンセリングや心療内科にいくのもなあ……。もう少し様子を見て、悪くなるようならそのときにもう一度考えてみます。
昨年12月から糖質制限ダイエットを続けていたのですが――大成功しました! 具体的には2か月で12キロの減量。目標体重を超えましたが、もう少し続けようと思います。といっても今までのように朝昼晩糖質をほぼほぼ摂らないというスタイルではなく、「夜は今まで通り、朝と昼は控えめに」という程度にしておきます。ちょっと緩和するわけですね。「糖質は絶対悪で糖質制限は一生涯続けるべき」というような風潮もあるようですが、「人生それすなわち食べること、好物は麺類と甘いもの」というタイプの人間にはもう無理です(´・ω・`)
ちなみに太っていたからダイエットをしたわけですが、その太った理由は自律神経失調症にあります。いわゆる過食というやつですね(過食嘔吐ではない)。
今年になって始めたPythonですが――超面白いです! 自分にあっているような気がします。今はCheckIOとCodeIQを利用して基本的な文法や命令を手に覚えさせつつ、『エキスパートPythonプログラミング』の学習を進めています。ゆくゆくはオープンソースのコードリーディングをしたいと考えいますが、いつになることやら(´・ω・`)